国際結婚・配偶者ビザ

worry
国際結婚・配偶者ビザについてについて、
このような不安はありませんか?
- 国際結婚の手続き方法や必要書類が分かりません
- お互いに離婚歴があるけど大丈夫ですか?
- 知り合ってから結婚までが短くて不安です
- 転職したばかりで収入が少ないです
- 昔、ビザ申請が不許可になったことがあった


このようなお悩み
私たちにお任せください!
国際結婚手続きや、配偶者ビザ申請のことなどは、インターネットで検索するとある程度の情報は出てくると思います。しかし、国際結婚の手続きは結婚相手の国籍により方法や書類が大きく異なりますし、手続方法が変更されるなどして、インターネットで出てくる個人のブログの情報は古い場合もあります。また、実際に情報を見ても、具体的にどのように対処すればよいのか、分からない方も多いのではないでしょうか?
当社では、このような国際結婚や配偶者ビザ申請に関する様々な疑問について、入国管理局の審査基準とこれまでの経験や実績をふまえ適切に回答するとともに、迅速かつ確実な国際結婚・配偶者ビザ取得に向けて、最大限サポートいたします!
お問い合わせ
CONTACT
まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話かお問い合わせフォームより受け付けております。

※面談、オンライン面談も平日の午前9時から午後6時が基本ですが、
事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」

国際結婚・配偶者ビザに関すること
配偶者ビザ取得の基本的な条件とは?
配偶者ビザ取得の基本的な条件とは? 日本人が外国人と結婚した場合、夫婦一緒に日本で生活するためには日本の配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザを取得するためには、単に結婚するだけでは足りず、お二人の婚姻が偽装結婚ではなく真実の結婚であり、これから日本で生活していくということを示す必要があります。以下に詳しく説明します。
① 法律上の婚姻関係が成立していること

配偶者ビザを取得するには、まずは法律上夫婦になる必要があります。法律上の夫婦とは、日本側でみれば、婚姻届を役所に提出して戸籍謄本にお相手のお名前が載ることを意味します。そのため、婚姻届を提出しない、内縁の配偶者は含まれません。
そして、法律上の夫婦といえるためには、原則的には、日本と相手の国と両方で婚姻手続きを行っていることが必要です。ただし、「法律上」とは、厳密には「日本の法律上」という意味になります。そのため、結婚相手の国で、何らかの事情で婚姻手続きが行えない場合でも、日本で婚姻届を出して婚姻が成立しているのであれば、「法律上の婚姻関係が成立していること」という条件を満たすことになります。
しかし、その場合はなぜ相手の国で婚姻手続きができないのか、その事情を説明するように入国管理局から求められる場合があり、そこで合理的な理由を説明することが重要となります。
相手の国の婚姻証明書が発行されない場合

上記のように、何らかの事情で相手の国で婚姻手続きができない場合があります。その場合、相手の国の結婚証明書が発行されません。しかし、入国管理局のホームページには、配偶者ビザの必要書類として「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要と記載されています。 お客様から、相手の国の結婚証明書が発行されないが大丈夫でしょうか?という問い合わせをもらうことが良くありますが、このような場合でも、配偶者ビザは許可されていますので大丈夫です。ただし、相手の国で婚姻手続きを行っていないことで、以下の②の婚姻が実体を伴うこと、という条件に引っかかる可能性はあります。そのため、相手の国の結婚証明書が発行されない場合、なぜ発行されないのか、なぜ婚姻手続きを行えないのかなどを、しっかりと説明することが重要です。
相手の国で婚姻手続きを行えない一例として、フィリピンの方と結婚する場合、フィリピン人側が過去に日本人と結婚していたことがある場合は、フィリピン側で婚姻手続きを行えない場合が多いです。というのも、お相手が過去に日本人と結婚していた場合、日本側では離婚できたもののフィリピン側で離婚できない、あるいは離婚手続きが全然進んでいないという場合があります。これは、宗教的な理由などからフィリピンでの離婚が難しくなっているためです。
その結果、日本側では離婚できたがフィリピン側では離婚できていないという状態になります。このような場合でも、日本側で離婚できているのであれば、その後に他の日本人と再婚することは可能です。ただし、フィリピン側では前の方と離婚できていないので、フィリピン側で結婚手続きはできません。この場合、フィリピン側での結婚証明書は発行されないということになります。
① 婚姻が実体を伴うこと

配偶者ビザにおいては、法律上の婚姻が成立していることはある意味当然の条件で、審査において問題となるのはこの「婚姻が実体を伴うこと」という条件の場合が多いです。婚姻が実体を伴うとは、夫婦が互いに協力し、助け合い、社会通念上の夫婦共同生活を営むことをいうとされています。そのため、例えば離婚しておらず戸籍上は婚姻関係にあったとしても、その婚姻関係が夫婦としての基礎を失っている場合には、配偶者ビザには該当しないということになります。
ただ、この婚姻が実体を伴うことという条件は、判断が難しい面もあります。というのも、実体を伴うかどうかというのは、突き詰めれば、お互いが想い合ってこれから夫婦として一緒に暮らしていきたいと考えているかどうか、という内心の問題ということもできるからです。そして、内心何を考えているのかは当人にしかわかりません。そのため、例えば実際に会ったのが1回だけだから偽装結婚で、会った回数が多いから真実の結婚だ、と断言することもできないのです。
そうはいっても、審査である以上は判断する必要があり、そのためにはある程度の基準が必要となります。婚姻が実体を伴うことという条件に対して明確な基準は公表されていませんが、概ね以下のような事情やそれを裏付ける資料から判断しているとされています。
- 知り合った経緯
- 交際に至る経緯
- 交際中の様子
- 結婚に至る経緯
- 現在の生活状況
- 将来の家族計画
- 相手が日本にいる場合は、配偶者ビザ申請時点で同居しているか
どういう状況であれば許可になり、何がダメというのは一律に決まっていないと思われます。ただ、例えばお互いにどうやって意思疎通をはかっているかとか、結婚するにあたって家族に紹介したとか、そういった具体的な事情は積極的に説明した方が良いといえます。
離婚歴がある場合
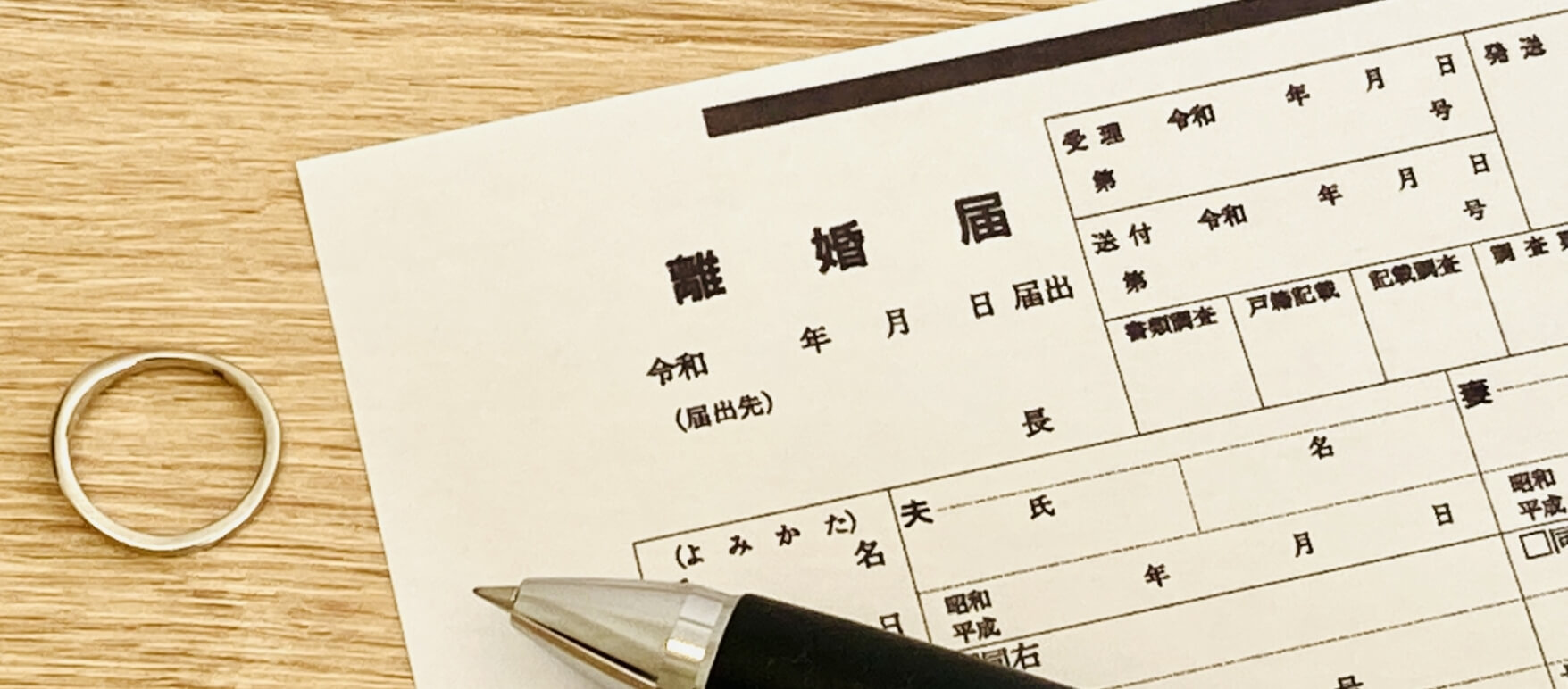
離婚歴があるが大丈夫かと心配される方がおられますが、一般的に離婚歴があるというだけで何か不利になるということはありません。ただ、日本人側が外国人と何回も結婚と離婚を繰り返している場合や、お相手が日本人との結婚と離婚を繰り返しているような場合、偽装結婚ではないかと疑われてしまう可能性があります。
もちろん、離婚する理由は様々なので、外国人との結婚回数が多いというだけで偽装結婚と判断されることはないですが、なぜ何回も外国人との結婚と離婚を繰り返すのかと疑問に思われる可能性もあるので、前の結婚の離婚原因なども併せて説明しておいた方が良い場合もあります。
また、前の婚姻期間中に今の配偶者と交際していた場合、いわゆる不倫状態で交際が始まった場合に、それが審査で不利になると思って交際に至る経緯などで嘘を付こうとする方がおられます。しかし、不倫状態で交際がスタートしたからといって、それだけで偽装結婚を疑われるということはありません。そのため、不倫状態だったというのであまり説明したくないのかもしれませんが、嘘はつかず事実通り説明すべきです。
交際期間が短い場合

知り合ってから結婚するまでが短く、偽装結婚を疑われないか心配されるかたがいます。この場合も、交際期間が短いというだけで不許可になることはありません。確かに、交際期間が短いと、知り合ってから結婚に至るまでの経緯が少なく、アピールできるエピソードが殆どないという場合もあります。しかし、じっくり交際してから結婚を決める方もいれば、直感で決めたという方もおられると思います。そして、知り合ってから少しの期間で直感で結婚を決めたからといって、それが偽装結婚と断言することはできません。
ただし、交際期間が短いとそれだけ説明できる事情や提出できる資料が少なくなってしまうので、短い期間ながらどのような経緯で結婚に至ったのか、しっかりと説得的に説明することが大切といえます。
年齢差が大きい場合

年齢差が大きい場合も、それだけで不許可になることはありません。ただし、年齢差が20歳以上であるような場合は、偽装結婚を疑われる可能性があります。実際、過去に偽装結婚で逮捕される方が多かった時代では、年齢差が大きいパターンが多かったことが原因ではないかといわれています。
もちろん年齢差が大きいとしても、きちんと交際して結婚に至ったのであれば、配偶者ビザを取得することは可能です。ただし、疑われやすいことには変わりないので、心持としては、交際経緯や結婚の経緯、これからの計画などをより丁寧に説明する方が良いと思います。
③その他のポイント
配偶者ビザの申請においては、主に上記の①②が重要な審査ポイントですが、その他にも、以下のような内容がチェックされています。
収入が少ない場合
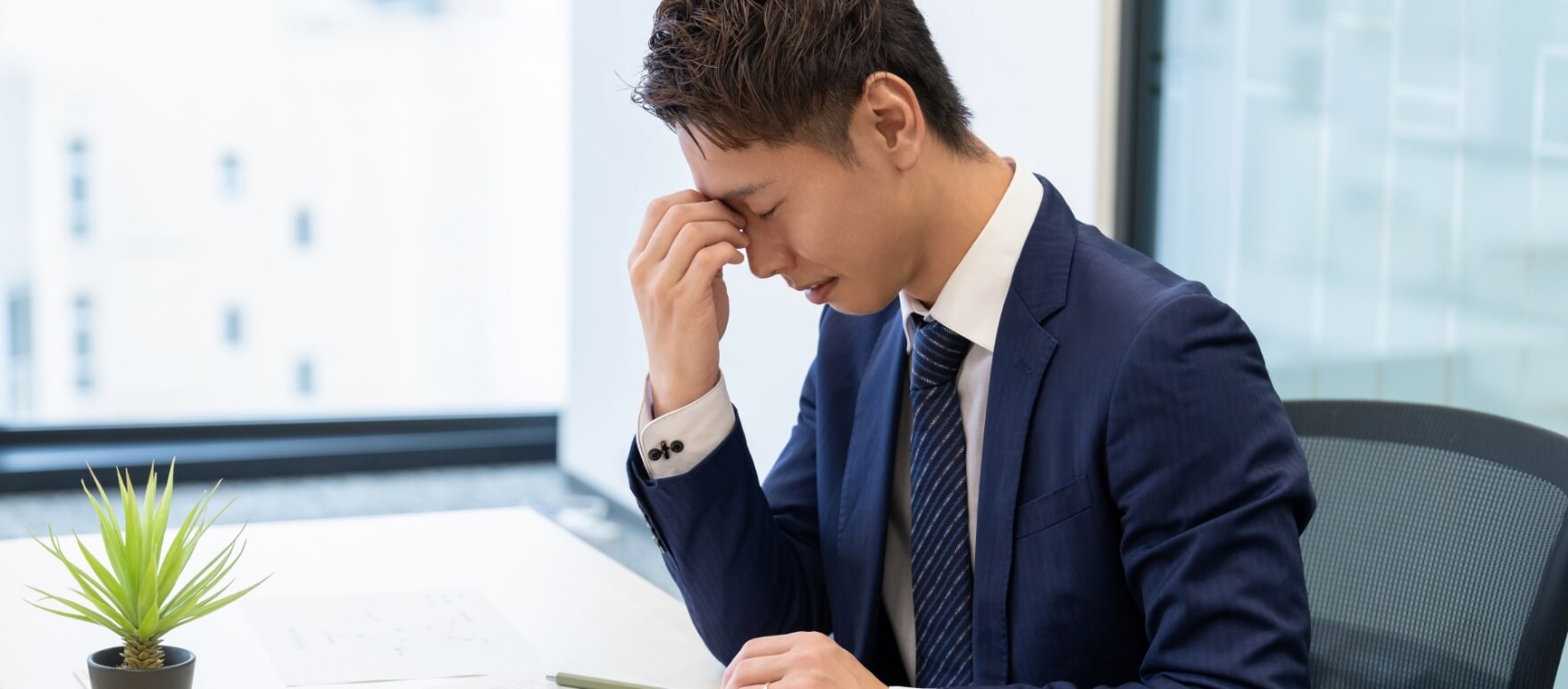
配偶者ビザ申請においては、これから夫婦がどのように日本で生活していくのか、という点の審査のため、夫婦の収入状況をチェックされます。基本的には、申請時点での日本人の在職状況、収入、資産などから判断されますが、お相手の方が日本の会社から内定をもらっており、来日後に働くことが確定しているような場合は、相手が得る予定の収入もふまえて判断されます。
収入について、月収が何円くらいだったら良いのかと質問されることがありますが、これはその時の日本人側の状況等によって異なるので、一概に決めることは難しいです。例えば、日本人が両親と同居しており両親を扶養している場合で、そこで相手と一緒に生活する場合は、両親と相手の3名を扶養していくことになるので必要とされる年収の基準は高くなります。また、自宅の家賃などが高い場合も、その分基準となる月収の水準は高くなります。
ただし、かなり余裕のある収入まで求められることはありません。無職であったり生活保護を受給するような水準である場合は問題になりますが、そのような水準でない限り、月収が低いというだけで不許可にはなりません。
また、去年の年収がほとんどなく役所発行の所得証明書上では年収がない場合でも、申請時点で働いており、給与明細書が3か月分程度提出できる場合は、収入面では問題なしと判断される場合も多いです。
過去に不許可歴がある場合

一度配偶者ビザを申請して不許可になった場合や、他のビザを申請して不許可になった場合は、次の申請はかなり慎重に進める必要があります。
配偶者ビザが不許可になった場合は、その理由をしっかりと入国管理局で確認する必要があります。電話では回答してくれませんが、窓口まで出向き理由を確認すれば、ある程度の範囲で原因は教えてくれます。そのうえで、次の申請の対策をしていく必要があります。
配偶者ビザが不許可になる場合としては、大きく分けて二つの原因があります。一つは、入管への説明が不足しており誤解を招いた、又は根本的に条件不足だったという場合です。このような場合は、説明が足りておらず誤解された箇所について詳細に説明し、補足資料を付けるなどして入管の勘違いであることを理解してもらう必要があります。また、根本的に条件不足の場合、例えば収入が少なすぎたような場合は、アルバイトを増やして収入を上げるように努力するなどしてから申請すれば、許可になる可能性があります。
もう一つは、入管に対して嘘の内容で申請してしまい、それが発覚した場合です。この場合は、虚偽申請を行ったということで次の申請もかなり厳しく審査されます。ただ、質問書作成の過程で相手との間に認識のズレが出てしまい、嘘を付いたつもりはなくても、結果として事実と異なる内容になってしまった、という場合はあると思います。そのような場合は、なぜ事実とずれてしまったのか原因をしっかりと説明し、謝罪して説明しなおすことが重要です。
配偶者ビザ以外のビザ申請が不許可となった場合は、その不許可理由によって配偶者ビザ申請に影響するかどうかが決まります。例えば、就労ビザを申請したところ、業務内容が就労ビザの条件に合わなかったという場合は、その次の配偶者ビザ申請に影響する可能性は低いです。ただし、就労ビザ申請時に噓の内容で申請したような場合は、上記と同じく虚偽申請をする人、と認識されてしまうので、次の申請は厳しく審査されます。
配偶者ビザ申請の必要書類とは?
日本人と結婚し配偶者ビザを申請する場合は、基本的には以下の書類が必要となります。
- 申請書
- 証明写真(縦4㎝✕横3㎝)
- 日本人の戸籍謄本(婚姻事項が載っているもの)
- 相手の国の役所から発行された結婚証明書
- 日本人の課税証明書
- 日本人の納税証明書
課税証明書が発行されない場合や、記載されている収入が少ない場合は、通帳のコピー、内定証明書や
雇用契約書のコピー、給与明細書のコピーなど、日本での生活費用を賄えることが分かる書類 - 身元保証書
- 住民票の写し
- 質問書
- 夫婦のスナップ写真 3枚程度
- 夫婦の交流が分かる書類(メールやSNSのやり取り、通話記録 等)
このように、実に多くの書類の提出が必要となります。また、これらの書類を準備して申請すれば必ず許可になるというものではなく、書類の内容が審査の基準を超えていることが必要となりますので、その検討・判断は簡単ではありません。
質問書に書くべき内容とは?

質問書とは、お二人の基本的な情報や交際経緯や結婚経緯などを記載する書類です。フォーマットは入国管理局のホームページに掲載がありますので、そちらをご確認ください。
質問書の中でも特に重要なのが、結婚に至った経緯を記載する箇所です。こちらについては、出会いの経緯や交際経緯が自然で、写真や通信記録など十分な資料を提出できる場合は、決まったフォーマットの枠内で記載して問題ないと思いますが、何らかのマイナスの事情がある場合や、決まったフォーマットでは書ききれない場合は、別の用紙で作成した方が良いです。作成する際は、手書きでなくてもパソコンで作成したものでも大丈夫です。
また、お二人の会話で使用している言語についても、お二人が普段どのように意思疎通をしているのかを確認する部分であり、意思疎通ができているとは言えないような場合は、偽装結婚を疑われる可能性があります。そのため、日本人側が相手の言語が分からない場合や、相手が日本語が分からないような場合は、どうやって普段会話しているのかを説明しておいた方が良いです。なお、翻訳機を使用して会話しているような場合でも、翻訳機を使っているからダメということはありませんので、その場合でも翻訳機を使って会話して問題なく意思疎通できている旨を説明するべきです。
その他、それぞれの親族を記載する欄がありますが、場合によっては家族に電話連絡が入って確認されることもあるので、記載間違いがないようにしっかりと確認して記載しておいた方が良いです。
書類を集めたら大丈夫?

配偶者ビザ申請では、必要とされる書類を集めて申請すれば許可になる、ということはありません。むしろ、書類を集めるのはスタートで、そこから具体的な内容を精査して、初めて可能性や問題点を詳細に検討できることになります。
上記の通り、質問書の記載内容は細かく確認されますし、書いている内容とそのほかの資料に整合性はあるかといった点や、過去の申請との相違はないのかという点など、様々な内容を検証されます。
そのため、書類を集めたうえでそれぞれの書類の内容や過去の経歴と照らしながら、全体として不自然なところはないか、といった目線で細かく確認する必要があります。
国際結婚の基本的な条件とは?
国際結婚は、状況によって定義が変わりますが、配偶者ビザの観点では基本的には日本人と外国人の結婚を意味します。日本人同士の結婚では、婚姻届に必要事項を記入し、必要に応じて戸籍謄本を添付して、最寄りの役所へ提出すれば結婚できます。しかし、結婚相手が外国人の場合は、結婚するための条件や書類などを相手の国の法律に基づいて検討する必要があるなど、婚姻届けを記載する以外の内容が非常に複雑になります。国際結婚の手続きにおいて確認すべきポイントは、婚姻の成立要件と婚姻の効力が及ぶ範囲の2点となります。
婚姻の成立要件

婚姻の成立要件としては、基本的には、結婚できる年齢になっていることや、独身であることといった、結婚する人の状態に関する条件と、必要書類を整えて婚姻届けを出すといった、手続き的な条件の二つを満たす必要があります。
そして、この成立要件については、結婚しようとするお二人それぞれについて、それぞれの国の法律によるとされています。例えば、日本人であれば日本の法律によりますし、外国人の場合はその外国の法律によります。
一例で行くと、結婚できる年齢について日本の場合は男女ともに18歳以上で結婚できるとされています。ただ、例えば女性の婚姻年齢が21歳とされている国の場合、日本人男性がその国の女性と結婚するのであれば、相手が20歳だと結婚できないことになります。
ただ、その国の規定で、婚姻する場合には婚姻手続きを行う国の法律を適用するという内容の規定があると、先に日本で婚姻手続きを行う場合、相手にも日本の法律を適用することになります。これを、反致といいます。
このように、国際結婚をする場合、日本人側は日本の法律で判断するとして、結婚相手について日本法律で判断するのか相手の国の法律で判断するのか、まずはそこの見極めが必要です。そして、相手の国の法律が適用される場合、相手の国の法律の規定を確認し、結婚できる状態にあるのかをチェックする必要があります。
また、法律で決まった要件についても一方的要件・双方的要件といって、一方だけに適用されるのか結婚する双方に適用されるのか、内容によって適用される範囲が変わりますので、国際結婚においては、結婚する相手に応じてしっかりとルールを検討・判断することが非常に重要です。
このように、婚姻手続きは一般的にそんなに難しい手続きではないと考えられているかと思いますが、国際結婚になりますと、相手の国籍によってはかなり複雑になってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
婚姻の効力が及ぶ範囲

国際結婚においては、基本的には、日本での婚姻手続きと、相手の国での婚姻手続きの両方が必要とされています。主な理由として、日本で婚姻届けを提出して結婚したとしても、それは日本では当然有効ですが、相手の国にそのこと届け出ないと、相手の国でも結婚の効力がでないからです。二人がいつ結婚したか、いつ法律上の夫婦になったか、というのは、先にどちらかの国で婚姻手続きを行った日で確定します。ただ、相手の国にとってみれば、自分の国でも手続きしなければ、結婚の効力は生じない、としている国は多くあります。
ただ、すべての国がそうというわけではなく、相手の国で正式に婚姻が成立したのであれば、自分の国でもその婚姻を認める、としている国もあります。この場合は、例えば日本で結婚出来れば、結婚相手の国で婚姻手続きをする必要がない、ということになります。
そのため、日本で成立した婚姻の効力が相手の国にも及ぶ場合、わざわざ相手の国で手続きをする必要がないため手続きの負担は軽くなります。
国際結婚の必要書類とは?
国際結婚手続きは、上記の通り日本と相手の国の両方で行うのが一般的です。ただ、その順番については特に決まりはありません。日本で先に手続きをしてその後に相手の国で手続きを行うか、相手の国で先に手続きを行って後で日本で手続きを行うか、そのどちらかです。
日本を先に行う場合

日本人については、本籍地のある役所で手続きをする場合、婚姻届と身分証明書以外には、特に書類は必要ありません。本籍地以外で手続きを行う場合は、戸籍謄本が必要です。
お相手については、婚姻要件具備証明書と呼ばれる書類が発行されれば、その書類と、後はパスポートか在留カードのコピーといった書類が必要になる場合が多いです。婚姻要件具備証明書が発行されない場合は、お相手の国の法律に基づき、婚姻できる条件を証明する書類が必要です。例えば、独身であることや、婚姻適齢を超えていること、両親の同意を得ていること等です。
ただし、お相手の書類については国ごとに全く異なりますので、事前に婚姻届を提出しようと考えている役所で確認することが重要です。
日本で先に結婚できた場合、次は相手の国でその旨を反映させることとなりますが、その手続きについても国ごとに大きく異なります。例えば、日本にある相手の国の大使館や領事館で行える場合もあれば、直接相手の国の役所で手続きする場合もあります。
基本的には、日本で婚姻届けを提出した後、戸籍謄本に婚姻した旨が反映されたら、その戸籍謄本と相手の国の言葉の訳文を用意して、それを提出することになる場合が多いです。ただし、提出する場合でも日本の外務省で事前に認証を受けてから提出するなど、そのまま提出すればよいというわけではなく、必要に応じて事前に日本国内でいくつか認証を受けておく必要がある場合もあります。
相手の国で先に行う場合

相手の国で先に行う場合、相手の国で婚姻届けに対応する役所で、事前にどのような書類が必要なのか確認する必要があります。これは、日本からでは難しいので、相手に母国で確認してもらうようにしましょう。
一般的には、法務局で取得した婚姻要件具備証明書や、戸籍謄本、及びその相手の国の母国語での翻訳文、それに対する認証が求められることが多いです。
相手の国で結婚できた場合、日本側の手続きは比較的簡単です。相手の国で結婚してから3か月以内に、結婚したことが載った結婚証明書とその日本語訳文、及び婚姻届を日本の役所に提出するか、又は相手の国にある日本大使館・領事館へ提出すればよい場合が多いです。
配偶者ビザ申請の審査期間は? 申請後は自由?
国際結婚手続きは、上記の通り日本と相手の国の両方で行うのが一般的です。ただ、その順番については特に決まりはありません。日本で先に手続きをしてその後に相手の国で手続きを行うか、相手の国で先に手続きを行って後で日本で手続きを行うか、そのどちらかです。
審査期間について

配偶者ビザ申請の審査期間は、海外から相手を呼び寄せるのか、相手が日本にいて今持っているビザから配偶者ビザへ変更するのかによって期間が異なります。
相手が海外にいる場合は、入国管理局で申請してから審査結果が出るまで、約1か月から3か月程度かかります。その後、入国管理局から許可されて在留資格認定証明書という書類が発行された後、それを相手に案内し、相手が現地の日本大使館・領事館で査証申請を行う必要があります。
相手が今日本にいる場合、今のビザから配偶者ビザへ変更する場合は、概ね1か月程度で結果が出ている場合が多いです。実際のところ、審査にどのくらいの時間がかかるのか、ビザ申請を専門に扱っている行政書士でも見通しを正確に立てることは困難です。というのも、審査期間自体は、申請したタイミングの入管の込み具合、申請した方の在留資格や状況、担当した審査官のスピードなどで前後してくるからです。
申請後について

配偶者ビザ申請は、基本的には申請した時点での事情で判断されるので、申請後に何かする必要があるということはありません。ただし、申請時点から状況が変わった場合、例えば、仕事を辞めたとか、一緒に住まなくなったという場合には、審査に影響するため注意が必要です。ただ、申請時点の状況と大きな変化がなく、そのまま普通に生活していれば、申請後の内容については特に気にする必要はありません。
お問い合わせ
CONTACT
まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話かお問い合わせフォームより受け付けております。

※面談、オンライン面談も平日の午前9時から午後6時が基本ですが、
事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」
配偶者ビザ・国際結婚の相談でよくある質問
Q3か月前に会ったばかりのパートナーと結婚を考えています。交際期間が短いと偽装結婚を疑われやすいと聞いたのですが、本当ですか?
A確かに、交際期間が短いことは配偶者ビザ申請の面ではマイナス事由にあたります。ただ、交際期間が短くても、お二人の交際経緯や結婚に至るまでの事情を丁寧に説明することで、配偶者ビザを取得することは十分可能です。当社では、交際期間3か月程度で配偶者ビザを取得された方は複数いらっしゃいます。
Qずっと無職で最近就職したばかりですが、配偶者ビザはとれますか?
A配偶者ビザでは、過去の年収よりも、これから安定した暮らしを送れる程度の収入があるかどうかが重要となります。そのため、今までずっと無職でも、申請時点で安定した収入を維持できていれば、配偶者ビザを取得できる可能性は十分ございます。
Q過去に複数回の離婚歴がありますが、問題はありませんか?
A外国籍の方との離婚歴が多い場合は、偽装結婚を疑われやすくなるため、入国管理局ではより一層慎重に審査が進められます。ただ、離婚歴があることだけで配偶者ビザが不許可になることはありません。お二人が真剣交際をしていることを詳細かつ丁寧に説明し、裏付け資料を提出することで、配偶者ビザを取得することは可能です。
Q過去に自分で申請して不許可になったことがあります。もう配偶者ビザを取ることはできないですか?
A過去に不許可歴がある場合、なぜ不許可になったのか、不許可理由を確認することが最も重要です。不許可理由をしっかりとフォローすれば、再申請して許可になる可能性は十分にあります。
Q外国側の結婚手続きがなかなか進みません。どうしたらいいですか?
A結婚相手の国によっては、役所の手続きが非常にゆっくり進むこともありますよね。ケースバイケースになりますが、最低限、日本側で婚姻手続きが完了していれば配偶者ビザが取得できることもあります。
Qパートナーとの年齢差が30歳以上あります。配偶者ビザは難しいですか?
Aご夫婦の年齢差が大きいことは、偽装結婚を疑われやすくなるため、入国管理局ではより一層慎重に審査が進められます。ただ、年齢差が大きいことだけで配偶者ビザが不許可になることはありません。出会いから結婚に至るまで、おふたりが真摯な交際を続けてきたことを詳細かつ丁寧に説明し、裏付け資料を提出することができれば、配偶者ビザを取得することは可能です。
Q家族から結婚を反対されています。配偶者ビザに影響はありますか?
Aご家族からご結婚を反対されていても、お二人の交際・収入状況に問題がなければ、配偶者ビザの申請に大きな悪影響はありません。ただ、入国管理局の審査の過程で、稀にご家族に対して電話調査が入ることがあります。ご家族が入国管理局の電話調査に対してきちんと対応してくれない可能性がある場合は、ご家族が結婚に反対しているという事情を事前に入管に説明しておいたほうが無難です。
Q仕事の都合で、パートナーとは日本国内で別居中です。配偶者ビザは取得できますか?
A配偶者ビザは、日本で配偶者と一緒に生活するための在留資格です。そのため、原則ご夫婦の同居が必須となります。日本国内で別居中ということは、現在お相手の方は別の在留資格をお持ちかと思うので、同居できるまでは別の在留資格で滞在することをおすすめします。もし、その他の特殊な事情がある場合はぜひ当社までお問い合わせください。
Q交際相手がオーバーステイ(不法滞在)中であることが判明したのですが、結婚手続き、配偶者ビザの申請はできますか?
A結婚手続きに必要な書類が揃っているのであれば、オーバーステイ中であっても結婚手続きは可能です。配偶者ビザの申請については、通常のビザ申請ではなく「在留特別許可申請」を行うことになります。当社では、オーバーステイ歴がある方、何らかの違反歴がある方のご依頼も承っておりますので、一度当社までお問い合わせください。
Q過去に離婚歴がある、交際期間が短い、実際に会った回数が少ない、といった事情がある場合、費用は高くなりますか?
A何らかのマイナスの事情があったとしても、それだけで直ちに依頼費用が高くなるということはありません。上記のような事情がある場合でも、当社でそのまま申請可能と判断した場合は、通常通りの費用で対応しております。 ただし、過去に申請が不許可になったことがありその理由を説明した方がよい場合など、通常の書類とは別に事情説明書を作成する場合には、内容に応じて費用を加算することもあります。その場合、事前に御見積書で費用を示しご依頼者様の承諾を得てから作成しますので、勝手に作成して追加費用を請求するということはありません。
Q必要となる書類は、全て代行で取得してくれるのですか?
A申請書や質問書といった作成する書類や、役所が発行する書類は全て当社が代行で取得可能です。しかし、国際結婚手続きで必要となる結婚相手の国で発行される書類など、お客様でしか準備ができない書類がありますので、そういった書類はご自身で準備していただくことになります。その場合でも、何を用意するのかは当社からご案内しますので、ご安心ください。
Q配偶者ビザ申請が不許可となってしまった場合はどうなりますか?
A不許可となった場合は、まずは当社で入国管理局へ出向き不許可理由を確認してきます。(ご希望があれば、お客様も同行頂いても構いません。)不許可理由を確認して、その内容に応じて次回の申請時期や対策を検証し、ご提案いたします。そのうえで再申請を当社へ依頼される場合は、交通費や公文書取得費などの実費を除き依頼費用はかかりません。なお、依頼費用の返金も可能です 。ただし当社からのヒアリングに虚偽の情報を提供していた場合など、不許可となった事情によっては再申請時一定の費用を頂戴したり、返金割合が変わる場合がございます。
Q忙しくて事務所へ行く時間が取れないのですが、必ず直接会って面談する必要はありますか?
Aご相談の方法として、当社へお越しいただいて面談する場合の他に、ZoomやSkypeなどを用いたオンライン面談の方法でも対応しております。また、お電話でのご相談でも対応可能ですので、直接当社へご来所頂かなくても構いません。
Q相談料はかかりますか?
A最初の面談や電話相談などは、無料で対応しております。当社でご事情をお伺いし御見積書を提示させていただいた後、後日にさらに相談を希望される場合は有料相談となります。
Qクレジットカードでの支払いは可能ですか?
Aはい、クレジットカードやQRコード決済に対応しています。(※QRコード決済は、当社へご来所頂いた場合のみご利用できます。)クレジットカードは、オンライン決済に対応していますので、オンライン面談や電話でのご相談の場合でもご利用いただけます。
Q交際相手が中国人で、まだ日本語が上手ではないのですが、交際相手に直接中国語でヒアリングすることは可能ですか?
Aはい、可能です 。当社では中国語スタッフが在籍しておりますので、交際相手の方のご連絡先や、Wechat などの SNS で繋いでいただければ、直接中国語で状況確認させていただきます。
配偶者ビザ・国際結婚に関するブログ記事
配偶者ビザ・国際結婚を行政書士に依頼するメリットとは?
配偶者ビザ・国際結婚手続きを行政書士へ依頼するメリットとしては、一般的には以下のような部分かと思います。
- ・行政書士に依頼することで、申請までの時間、許可の可能性、
手間の軽減や精神的な負担が軽くなります
- ・行政書士は詳細にヒアリングを行い、要件を満たしているか確認します。
許可を阻害するマイナス面がある場合でも、ある程度フォローする方法を知っています
- ・行政書士は審査を有利に運ぶためのノウハウを持っており、
申請理由書のクオリティを高めることができます
当社へ依頼するメリット
merit 01

経験豊富な行政書士が対応
国際結婚・配偶者ビザ専門の行政書士が丁寧にご事情をお伺いし、ご不安点に対する解決策を提案します。配偶者ビザのみならず、これから生まれてくるお子様の国籍や出生届に関するご質問など、ご家族皆様のお悩みについても対応可能です。
merit 02

オンライン対応可能
ご相談からご契約、申請まですべてオンライン・郵送・お電話で対応可能です。そのため、当社にご来社いただく必要はありません。日本全国・日本国外からのお問い合わせも承っております。
merit 03
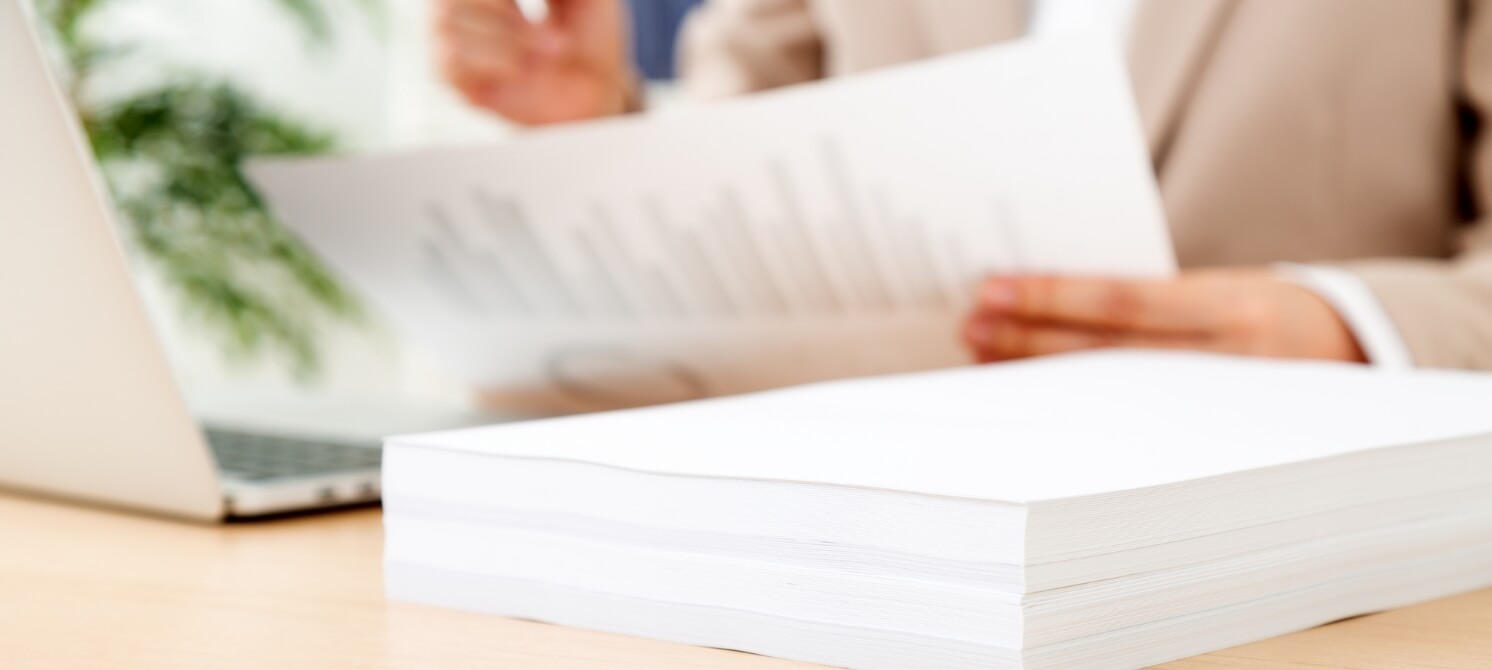
書類作成フルサポート
配偶者ビザ申請では、お二人の交際経緯を丁寧に説明し、立証資料を提出することが非常に重要です。ご夫婦の状況をヒアリングした上で、書類作成はすべて当社で行います。また、公文書も当社で代行取得しますので、スムーズな申請が可能です。
当社へ依頼した場合の流れとは?

ご相談
ご相談は、まずはお電話かメールにてご相談ください。
初回の相談は無料で対応しております。
電話相談受付時間:
(平日)午前9時~午後6時
24時間受け付けています。1営業日以内にご連絡いたします。
※面談、オンライン面談も平日の午前9時から午後6時が基本ですが、
事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」
一度ご連絡頂いた後は、Wechat 

相談は、当社での面談、オンラインシステム(Zoom、MicrosoftのTeams、Skype)を用いた面談、お電話にて対応可能です。
ご相談だけの場合は費用は掛かりません。
ご事情を確認したうえ、許可の可能性と、申請までの流れなどを当社からご説明し、当社へ依頼頂いた場合の費用のお見積りを提示致します。


必要書類の収集
役所から取得する公文書などを当社で収集し、お客様自身で取得いただく資料などについてご案内致します。
また、書類作成のため必要となる事項について、ヒアリングを行います。

申請書や質問書などの作成
資料収集とヒアリングが概ね完了しましたら、当社で申請書や質問書などの書類を作成いたします。
作成後、お客様にて確認いただき問題なければ、申請を行います。

申請
申請は、当社の行政書士が行いますので、お客様が入国管理局へ行く必要はありません。
申請が完了しましたら、入国管理局から交付される申請受付票をお渡しいたします。
申請が受け付けられましたら、費用の残り半分をお支払い頂きます。

結果の受取
申請から、概ね1ヵ月から3か月後に審査の結果が出ることが多いです。
日本国外にお住いのお相手を呼び寄せる場合、許可証はメールでご案内可能であるためスムーズな手続きが可能です。
すでに日本在住の方については、当社にて配偶者ビザの在留カードを受け取りに行きますので、
お客様が入国管理局へ出向く必要はありません。
お問い合わせ
CONTACT
まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話かお問い合わせフォームより受け付けております。

※面談、オンライン面談も平日の午前9時から午後6時が基本ですが、
事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」
配偶者ビザ・国際結婚の依頼費用について
国際結婚手続き


短期滞在ビザ申請


配偶者ビザ申請


※上記料金には、交通費や通信費、公文書発行費用、収入印紙代は含まれておりません。
※具体的な金額は、ご相談時にご事情を確認のうえ、詳細な金額のお見積書をご提示致します。
ご相談とお見積もりの提示までは、特に費用は掛かりませんのでご安心ください。
お問い合わせ
CONTACT
まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話かお問い合わせフォームより受け付けております。

電話相談受付時間:
(平日)午前9時~午後6時
24時間受け付けています。1営業日以内にご連絡いたします。
※面談、オンライン面談も平日の午前9時から午後6時が基本ですが、
事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」


